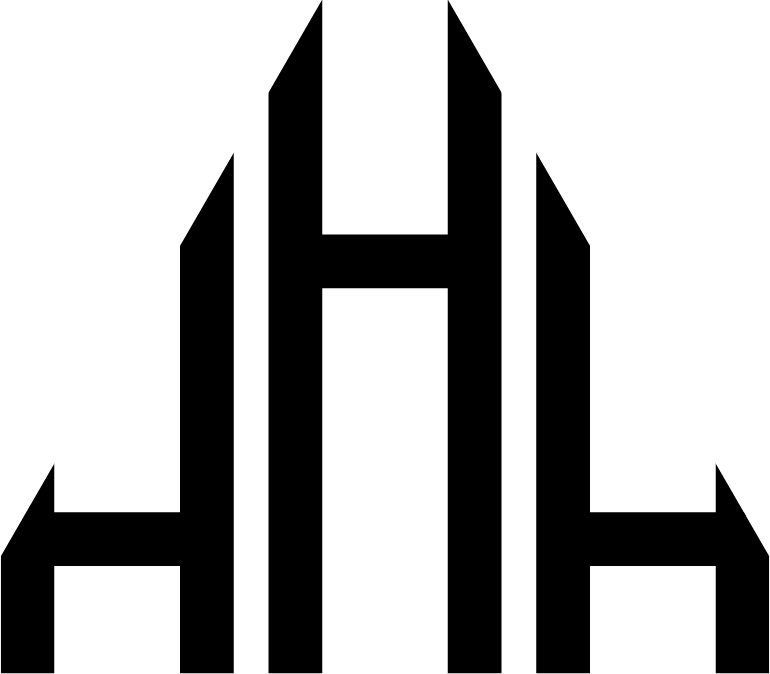【雑学】登山道に積んである石、あれ何?
登山を始め、あらゆる山で見かけた積んである石。
何となく上に石を積んだり、写真撮ったりしてきたけど、あれの正体を調べてみます。
- 雑学
結論
結論から言うと多くの場合、道標(みちしるべ)であることが多いとのことです。
あの積んである石のことをケルン(cairn)というらしいですが、天然では生じない人工的に積み上げられた積み石のことらしいです。
「天然ではありえない積み石」であることが道標として認識されやすいんだと思います。
AIにケルンについてを訊ねると「石の大きさや形、積み上げ方によって、目的地や分岐点を示している。」とありました。
現代の登山は「YAMAP」などの登山地図アプリや登山道の整備によってケルンの道しるべとしての意味合いは薄れていますが、過去の登山文化の名残として、歴史を感じるモニュメントだとしみじみ思います。
以降はケルンの別の役割について調べた範囲で書いていきます。
山頂
山頂でケルンを見かけることも多いですが、これは道標というより、山頂を示すための目的である可能性があるそうです。
これも過去の登山文化の名残っぽいと思いますが、現在は登頂の記念的な意味合いがあるかと思います。
願掛け
願いを込めて積み石をすることもあるそうです。
特に宮崎県人は、高千穂の天安河原(あまのやすかわら)での石積み祈願で、願いを込めて石を積むという文化があるので、山頂という特別な場所で願いを込めてケルンを積む人も多いと思います。
宗教や信仰のモニュメントである可能性もあるそうです。たぶんこういう場合は近くに看板なり文字が彫ってある石碑なりがあるとは思います。
慰霊碑
故人や故郷への追悼や感謝を表して積み上げられている場合もあるそうです。
つまり登山や山での事故・遭難による故人への慰霊を意味するということです。
一本道など、どう考えても迷わない登山道にケルンがある場合は、もしかしたら慰霊目的かもしれません。
そういった可能性もあるので、ケルンを不用意に蹴ったり、その上に座ったりしないほうが良さそうですね。
境界線
土地や領域の境界を示すためにケルンを設置している場合があるそうです。
これも道標同様、昔の文化の名残だと思います。
まとめ
ケルンは道標だったり願掛けだったりと意味は様々で、もちろんココで書いた以外の目的もあると思います。
登山のモニュメントとしてケルンを眺めたり、慰霊や願掛けの意味を込めて石を積んでみるといいかもしれません。
最後までご覧いただきありがとうございました。