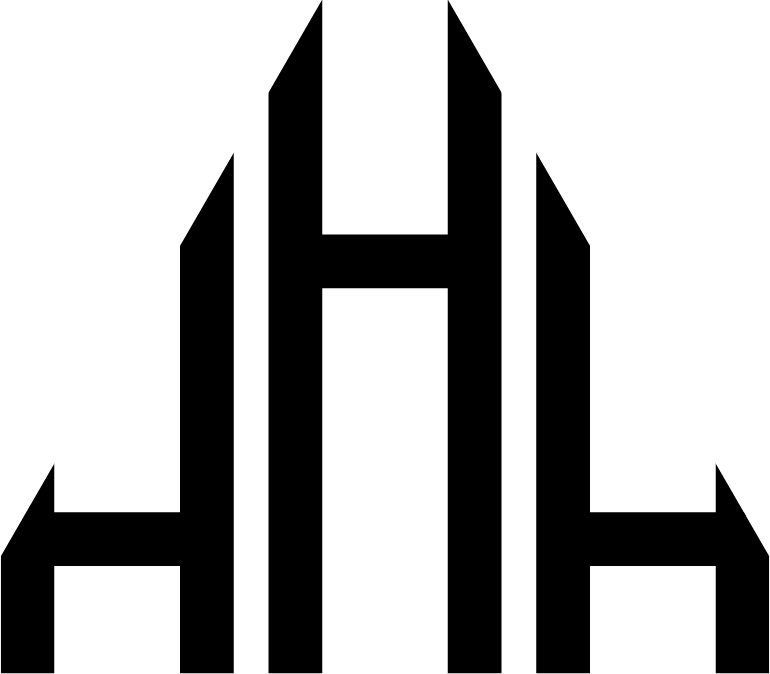脱初心者!登山のためのトレーニング
より高く、より速く、より楽しく登るため、登山のためのトレーニングについて調べてみました。
バテなくするためにも、ケガを防止するためにもトレーニングは有効なので是非最後までご覧ください。
- トレーニング
登山のためにトレーニングは必要?
登山は以前の記事「登山のダイエット効果」でも書いた通り、かなりのエネルギーを消費するハードな運動です。
そのためスタミナや筋力など、フィジカル(総合的な身体能力)が必要になります。
当然ですが、登山の経験値や自分のペースで無理なく登るということも重要ですが、登山を目標に据えたトレーニングを行うことが登山の質と楽しさを高めてくれるはずです。
登山で必要なフィジカル
様々な登山関連の書籍や論文、ウェブサイトを見ましたが、共通して必要なものは以下の4つがあげられていました。
- 体力(持久力)
- 筋力
- バランス感覚(体幹)
- 柔軟性
当記事では上記の4項目別にトレーニング方法を紹介・解説します。

体力の向上
登山では持久力はとても重要で、長時間に及ぶコースでは息切れや疲労感によって集中力がなくなり、事故や怪我のリスクが増加します。
体力を向上させることで集中力を保ち、更に景色を楽しむ心のゆとりも得られるはずです。
-
ウォーキング・ランニング
長時間、一定のペースで歩き(走り)続けることで持久力を向上させます。
ポールを使ったりザックに重りを入れて行うことで登山をより想定したトレーニングを行うことができます。
-
水泳
全身を使うことができる水泳はとても優秀な有酸素運動で、間接など体への負担が少ないのもおすすめです。
-
サイクリング
日常に取り入れやすい運動かつ、負荷を調整しやすいのも良い点です。
-
傾斜トレッドミル
ジムにある傾斜を調整できるトレッドミル(ランニングマシン)を使用したトレーニングです。
傾斜を10度ほどにし、登山に近い負荷でトレーニングを行います。
速度や傾斜を調整することで自分の体力レベルにあったトレーニングができるのでジムを利用している方にはおすすめです。
ちなみに著者がやってみたところ、脚の筋トレを定期的にやっているにも関わらず、強烈な筋肉痛が来ました。

筋力トレーニング
登山では基本的にザック(リュック)を背負いますがこれがなかなかな重量です。
装備の重量に加え、急な坂や岩場の登攀や鎖場で脚力や背筋力など様々な筋肉を駆使することになります。
瞬発力で発揮する筋力と、長時間の運動を支える筋持久力をバランスよく鍛えることが登山においては大切だと思います。
-
スクワット
脚力や体幹を鍛えるのに良い種目で、優れたトレーニングにも関わらず、どこでもできるのも利点です。
フォームによってはヒザを痛めることにもなるので、曲げた膝がつま先よりも前に出ないよう、椅子に座るようにお尻を後ろに引くように行うのが良いです。
難しい人は、ハーフスクワット(完全にひざを曲げ切らず、半分くらい膝を曲げる動作)で行うのも効果があります。
-
ランジ
片足を前方に出し軽く曲げ、もう片方の脚を後方に伸ばす、いわゆるアキレス腱を伸ばすようなフォームでスクワットを行うトレーニングです。
バランスを取るのにも筋肉が使われ、股関節の柔軟性も得られる良いトレーニングです。
-
背筋トレーニング
ザックを背負うことや、ロープ・鎖を使って登る時に背筋力が必要になります。
チンニング(懸垂)やラットプルダウンなどが有効なトレーニングですが、設備や器具が必要なのが難点です。
背筋は引く動作で鍛えることができます。おすすめなのはゴムのチューブを使ったトレーニングで、自宅でも手軽にトレーニングができ、場所も取らないし安価なのも優秀な器具だと思います。
-
インターバルトレーニング
有酸素運動にも通じるトレーニングで、高強度なトレーニングと休憩を繰り返すことで心肺機能を向上させます。
例えば傾斜トレッドミルで1分間全力で登り、1分休憩する。このセットを10本行うといった感じです。
短時間で心拍数を上げることができ、有酸素運動と筋力トレーニングどちらの恩恵も受けられる良いトレーニングですが、めちゃくちゃきついので、自分に合った強度と時間の設定を行うのがポイントとなります。

バランス感覚・体幹トレーニング
山道は日常で歩くような平坦な道ではなく、足場が悪く傾斜や凹凸が多く、踏むと崩れるような不安定な箇所もあります。
バランス感覚が不足すると、転倒や滑落のリスクが高まります。
バランス感覚や体幹を鍛えるメリットは姿勢改善、腰痛肩こり対策にもなるので日常生活においても実感できます。
-
プランク
自重体幹トレーニングの代表的な種目です。
肘とつま先を床につけた状態を1~2分キープします。これを3~5セットを目安に行います。
横から見たときに頭、肩、腰、ヒザが一直線になるようにします。お尻を上げすぎないようにしましょう。
片手・片足を上げるツーポイントプランクや、腕立て伏せのようなフォームのハイプランクなどのバリエーションもあります。
-
片足立ち
とても手軽に行うことができるバランス感覚を鍛えるトレーニングです。30秒以上キープするのを目安にすると良いらしいです。
片目を閉じたり、手を挙げながら行うなどのバリエーションがあります。
手軽にできますが、バランスが崩れると危ないので周囲の安全の確保のうえ行ってください。
-
バランスボード
乗ってバランスを保つことでバランス感覚や体幹を鍛えることができるトレーニング器具です。
バランスボードに手を付いてプランクを行うこともできるなど、体幹トレーニングの幅が広がります。

柔軟性
登山に限ったことではありませんが、筋肉が硬いと血行が悪くなったり関節の可動域が狭まりケガのリスクが高まります。
登山では長時間に渡って荷物を背負いながら歩くので、筋肉が披露し痛みが出やすくなります。
これらを防ぐためにも柔軟性が必要です。
-
ストレッチ
ストレッチにはダイナミックストレッチとスタティックストレッチがあります。
分かりやすくいうと、ダイナミックストレッチはラジオ体操のように反動を付けて反復して行うもので、スタティックストレッチは前屈のようにグイグイとフォームを固定して行うものです。
登山においては、股関節・肩甲骨・ふくらはぎのスタティックストレッチを行うのが効果的で、歩行の効率や疲労軽減につながるとされています。
ストレッチはグイグイと痛いまでやりすぎるとケガのリスクが高まるので、痛た気持ち良いで止めるのが効果的です。
また、登山直前にはウォームアップを兼ねて、ダイナミックストレッチを行うのが良いです。
-
ヨガ
柔軟性だけでなく、体幹トレーニングにも効果的な運動です。
ヨガは動画も多く出ているので参考にすると良いですが、初心者がいきなり難度の高いポーズをするとケガをするので注意してください。
先述したダイナミックストレッチのように、ヨガにもフロウヨガという流れるような動きで次々にポーズを変えていくものがあります。個人的にはこっちのほうが有酸素運動にもなるのでおすすめだと思います。
-
ピラティス
柔軟というより体幹トレーニングに重きを置いたエクササイズですが、柔軟性の向上にも期待できます。
呼吸を意識し、ゆっくりと動きながら筋肉を使ったエクササイズを行います。
その見た感じとは異なり、初めてやった時は最後まで付いていけないほどキツかったのを覚えています。
ケガのリスクも低く、柔軟性だけでなく多方面に効果のあるエクササイズなので、たまにトレーニングに導入するのもよいと思います。
まとめと今後のトレーニング紹介について
より高い山、高難度の山を目指すうえでも、バテ・ケガ防止のためにもトレーニングは大切だと思います。
当記事では登山におけるトレーニングについて、広範囲で書いていきました。
今後はおすすめのトレーニング種目を深堀りしてご紹介できたらと思います。
最後までご覧いただきありがとうございました!